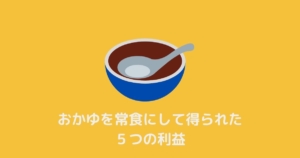『ライオンのおやつ/小川糸』を読んで【内容(ネタバレなし)】

あらすじ
余命宣告された30代前半の独身女性の雫は、残りの日々を瀬戸内のレモン島と呼ばれている島のホスピスで過ごすことを一人で決めました。
そこでは、毎週日曜日、入居者がもう一度食べたいおやつをリクエストして、みんなで食べる「おやつの時間」があるのです。
リクエストされるおやつには、それぞれの想いが詰まっているのです。
雫を中心に、取り巻く人々の多種多様な生きる姿が描かれています。
ジャンル・ボリューム
日本の小説、255ページ。
ホスピスという舞台であることや主人公の雫自身の気持ちにひきずられ、死に向かっていくのだろうと、若干気持ちも重いまま読むスピードもややゆっくりめにスタートしました。
しかし、雫の生きる喜び、楽しさ、毎日のキラメキに出会うたびにどんどんと読むスピードが加速して、雫の毎日が楽しみになって、最後まで一気に読んでしまいました。集中力が途切れず、夢中に読めるちょうど良いボリュームだと感じました。
2020年本屋大賞にノミネートされていた『ライオンのおやつ/小川糸(ポプラ社)』です。
惜しくも大賞を逃し2位でしたが、良い本です。出会えて感謝します。
(この年の大賞は『流浪の月/凪良ゆう(東京創元社)』でした。)
『ライオンのおやつ/小川糸』を読んで【蘇(そ)の作り方】
蘇(そ)の作り方

蘇は、奈良時代や平安時代から食べられていた古代の乳製品です。牛乳を煮詰めて作ります。
引用元/https://tukushi294.com/so/
蘇(そ)の作り方は、別の記事に書きました。興味のある方は、こちらの記事も読んでみてください。
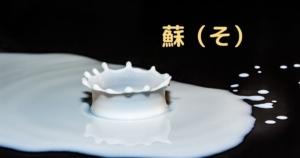
蘇(そ)が売ってました!
注意点は、クール便発送なので、商品代金と合わせて考えなくてはなりません。
商品代金より送料が高い場合があります!
『ライオンのおやつ/小川糸』を読んで【粥有十利(しゅうゆうじり)とは】
粥有十利(しゅうゆうじり)とは、曹洞宗の宗祖である道元禅師が食事をするときの作法として著した「赴粥飯法(ふしゅくはんぽう)」に書かれている、お粥を食べることによって得られるの10の利益のことです。
食欲がないときや病の時に、おかゆには助けられます。
興味がある方は、こちらの「おかゆを食べて良かった5つの利益【粥有十利(しゅうゆうじり)】」の記事も読んでみてください。
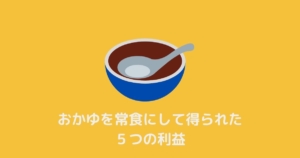
その他気になる言葉【QOL・QOD・モルヒネワイン・ワインの涙】
QOL生活の質
QOLは生活の質と言われますが、どういう意味なのでしょうか。
ただ単に生きることではなくて、どうよく生きるかということと説明されることがありますが、人によって「良い」と感じること、つまり価値観が違うので、定義をするのが少し難しいです。
自分が充実している、心が満たされていると感じる。それは、なんなのか。
加齢や病気で、できていたことが出来なくなっていったときに、どのようなサポートをしてもらって、もしくは出来るだけサポートしてもらわないで、何をやり続けたいのか。状況に応じて、体や心の変化に合わせて、日々、修正してくものなのでしょう。
QOD死に方の質
QODは死に方の質と言われます。良い死に方って、一体なんでしょうか。
人に迷惑をかけないで死にたいと思う人が多いようです。
そうなると、自分の人生を全うしたと思えて、残された家族を困らせないで、火葬から埋葬までの準備も全て整えているような最期が理想の死と私は感じます。
この「ライオンのおやつ」の主人公の雫ちゃんも、そうやって準備して、QOLを高めながら、同時にQODの整えていっていました。
モルヒネワイン
末期癌の患者のように、痛みと咳などで苦痛を伴うときに、モルヒネワインのような苦痛を取り除き、笑って生きるためのモルヒネの使い方は、きちんとお医者さんが処方すれば依存症にならず、死期を早めることにはならないと言います。(参考/特定非営利活動法人 日本緩和医療学会サイトより)
PCAという、痛くなったら患者本人がボタンを押して、決まった量だけ鎮痛剤が出るような鎮痛の装置が「ライオンのおやつ」の本の中にも出てきました。
痛みをコントロールすることは、緩和ケアの一番大事なことで、そのためにもモルヒネとPCAの使い方がポイントになるように感じます。
もしも、自分が緩和ケアにお世話になりたくなったら、まずは処方できるお医者さんを探したいと本を読んで思いました。
ワインの涙
アルコール度数の多いワインで見られるワイングラスの内側にできる、絶え間なくカーテンのように流れ落ちる液滴のことをワインの涙と言うのですね。
若い赤ワインではなく、完熟したフルボトルの赤ワインを思い浮かべます。

夜間セデーション
夜だけ睡眠薬を使ってしっかり眠ることを指します。夜寝られると、朝にスッキリ目覚めるので、起きている時の生活の質が向上するのだそうです。

まとめ【『ライオンのおやつ/小川糸』を読んで】

本を読み終えて、これからの生き方、身の回りの持ち物の整理、人生でやり残していると思うものについて考えました。
良い死に方が描かれているこの本を読むことは、よりよく生きるとはどう言うことか、考えるきっかけになります。
良い本に出会いました。
NHKのドラマも良かったです。
機会があれば、是非おすすめします。